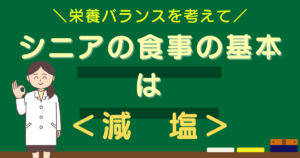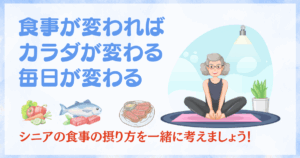「血糖値が気になる」「家族に糖尿病の人がいるから不安」という方も多いでしょう。
糖尿病は食生活の見直しで予防できる病気です。
本記事では、シニア世代が取り入れたい血糖値を安定させる食事の工夫や、日常で意識すべき食習慣を分かりやすくまとめました。
シニアが糖尿病になりやすい理由
シニア世代は糖尿病になりやすいため、日常の食生活に注意が必要です。
年齢とともに体の代謝機能が落ち、血糖値のコントロールが難しくなるからです。
加齢による筋肉量の減少や運動不足が挙げられます。
筋肉には、糖をエネルギーに変えるという重要な役割があるのですが、筋肉が減ると余分な糖が血液中に残りやすくなります。
味覚の変化で甘い物や濃い味を好むようになり、糖質や塩分を摂りすぎてしまうことも影響します。
若い頃と同じような食事を続けていると、糖の処理能力が追いつかず血糖値が上昇しやすくなります。
これがシニアに糖尿病が多い大きな理由です。
血糖値を安定させる食事の工夫
血糖値を安定させるには、毎日の食事の工夫が大切です。
急激な血糖値の上昇を防ぐことで、糖尿病予防につながります。
以下で詳しくお伝えします。
食物繊維を意識して摂る
<食物繊維の働き>
便通を整える
水分を吸収して便をやわらかくし、腸のぜん動運動を促すため、便秘の予防や改善に役立ちます。
血糖値の上昇を抑える
糖の吸収をゆるやかにするため、食後の急激な血糖値上昇を防ぎ、糖尿病予防にもつながります。
コレステロールを下げる
胆汁酸やコレステロールを吸着して体外に排出しやすくし、動脈硬化や心疾患の予防に役立ちます。
腸内環境を整える
善玉菌のエサになり、腸内フローラを改善して免疫力向上や大腸がん予防に効果が期待されます。
<食物繊維の種類と特徴>
食物繊維は大きく「水溶性」と「不溶性」に分けられます。
水溶性食物繊維
特徴:水に溶けてゲル状になり、糖や脂質の吸収を抑える。腸内細菌に発酵されやすい。
主な食品:海藻(わかめ・昆布)、果物(りんご・柑橘類)、こんにゃく、オーツ麦、豆類
働き:血糖値上昇を抑制、コレステロール低下、腸内環境改善。
不溶性食物繊維
特徴:水に溶けにくく、便のかさを増やして腸を刺激する。
主な食品:野菜(ごぼう・キャベツ)、きのこ類、豆類、穀類(玄米・小麦ふすま)
働き:便通改善、腸内の有害物質排出。
<シニアにおすすめの食物繊維の摂り方>
- 主食で工夫する
白米だけでなく、雑穀米・玄米・オートミールを取り入れると、不溶性食物繊維が自然に増やせます。パンなら全粒粉パンがおすすめです。 - 毎食に野菜を加える
厚生労働省は「1日350gの野菜摂取」を推奨しています。生野菜だけでなく、煮物・蒸し野菜・味噌汁の具にすることで、量を無理なく増やせます。特にごぼう・ブロッコリー・ほうれん草は食物繊維が豊富です。 - きのこ・海藻を常備する
しいたけ・えのき・しめじなどのきのこ類は低カロリーで食物繊維が豊富。さらにわかめ・昆布・もずくなどの海藻類は水溶性食物繊維を効率的に補えます。毎日の味噌汁やサラダに加えると手軽です。 - 果物はデザート感覚で
りんご・バナナ・みかん・キウイなどは水溶性食物繊維が多く、朝食や間食に取り入れるのにぴったり。ただし果糖の摂りすぎに注意して、1日1~2個を目安にしましょう。 - 豆類を上手に使う
大豆・黒豆・レンズ豆・インゲン豆は両方の食物繊維を含み、たんぱく質も補えます。煮豆やサラダ、スープに加えると栄養バランスも良くなります。
<シニア向け食事法まとめ>
シニアの1日あたり食物繊維の目安量
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、1日あたりの食物繊維の目標量は次のとおりです。
男性(65歳以上):21g以上
女性(65歳以上):18g以上
実際には平均摂取量が不足しがちで、多くの方が2〜5gほど足りていないといわれます。
食物繊維が不足しないための工夫
毎食ごとに「野菜+きのこor海藻」を入れる
主食を精製度の低いものに切り替える(雑穀米、オートミールなど)
果物や豆類を間食や副菜に活用する
このように「少しずつ積み重ねる」のがコツです。
簡単な献立例(1日分)
朝食
オートミール+ヨーグルト+キウイ(食物繊維:水溶性)
野菜たっぷり味噌汁(キャベツ+わかめ+しめじ)
全粒粉トースト
昼食
雑穀ごはん
鶏肉とごぼうの煮物(不溶性食物繊維が豊富)
ほうれん草のお浸し
みかん
夕食
焼き魚(副菜で大根おろしを添えるとさらに◎)
ひじきと大豆の煮物
ブロッコリーとトマトのサラダ
きのこ入り味噌汁
このような献立なら、1日20g以上の食物繊維を自然に摂取できます。
糖尿病予防には、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランスよく摂ることが大切です。
食物繊維のバランスのとり方
水溶性:不溶性=1:2の割合が理想とされています。
例えば、
ごはん(不溶性)
わかめの味噌汁(水溶性)
野菜炒め(不溶性)
果物(水溶性)
といった組み合わせがバランスの良い(1:2の割合)食事になります。
食物繊維は腸内環境を整えるだけでなく、糖の吸収を遅らせる働きもあるため、糖尿病予防に役立ちます。
食物繊維を意識して血糖値をコントロールしましょう。
主食・主菜・副菜のバランス
糖尿病予防には、主食・主菜・副菜をバランスよく組み合わせることが大切です。
例えば、白米だけを多く食べると血糖値が急上昇しやすいのですが、魚や肉、野菜を加えることで吸収のスピードがゆるやかになります。
「炭水化物は控えたほうがいいかもしれない…」と思う方もいますが、完全に抜くのではなく、組み合わせを工夫しましょう。
どれかに偏ると栄養が不足したり、血糖値が乱れやすくなるので、主食・主菜・副菜のバランスを常に意識しましょう。
間食の工夫
間食を完全に我慢する必要はありません。
工夫次第で、糖尿病予防に役立つおやつに変えられるからです。
間食を上手に工夫して、糖尿病予防に利用しましょう。
関連:実践を続けるために
- シニアのための減塩レシピ — 砂糖だけでなく塩の摂りすぎも同時に見直す。
- 60代に必要な栄養素と摂り方 — たんぱく質・ビタミン・ミネラルの“抜け漏れ”を防ぐ。
糖尿病予防におすすめの食材
糖尿病予防には、血糖値の上昇を緩やかにする食材を取り入れるのが効果的です。
日々の食事で無理なく続けられる食材を選ぶことがポイントです。
食材の性質を理解しましょう
食物繊維を多く含む野菜や海藻、きのこ類は消化吸収をゆるやかにし、血糖値の急上昇を防ぎます。
魚や鶏肉などの良質なたんぱく質は、筋肉維持に役立ち、代謝を支えます。
玄米や全粒パンといった精製されていない穀物は、白米や食パンに比べて血糖値を上げにくい特徴があります。
これらを意識的に取り入れることで、糖尿病予防に役立つ食生活を無理なく続けることができるでしょう。
日常で注意したい食習慣
糖尿病を防ぐためには、食材だけでなく食習慣も大切です。
理由は、食べ方や生活のリズムが血糖値の安定に直結するからです。
早食いや夜遅い食事は血糖値を急上昇させやすく、肥満や糖尿病のリスクを高めます。
間食のとりすぎや清涼飲料の常用も要注意です。
<糖尿病予防におすすめの食習慣3つ>
よく噛んでゆっくり食べる
規則正しい時間に食事をとる
飲み物は水やお茶を中心にする
このような3つの習慣の積み重ねが、糖尿病予防の大きな力になります。
まとめ|予防は日々の食事から
シニア世代にとって糖尿病予防は、特別なことではなく日々の食事から始まります。
この「日々の食事」がとっても大切なんです。
次の3つを常に意識しましょう
食物繊維や良質なたんぱく質を意識して摂る
主食・主菜・副菜をバランスよく組み合わせる
食習慣を整え、無理なく続ける工夫を忘れない
「少し意識するだけで変われるかもしれない」と思いながら取り組むことが、予防への第一歩です。
小さなことを続けなければ、小さな積み重ねにはなりません。
「日々の食事」を積み重ねて、健康寿命を延ばしていきましょう。
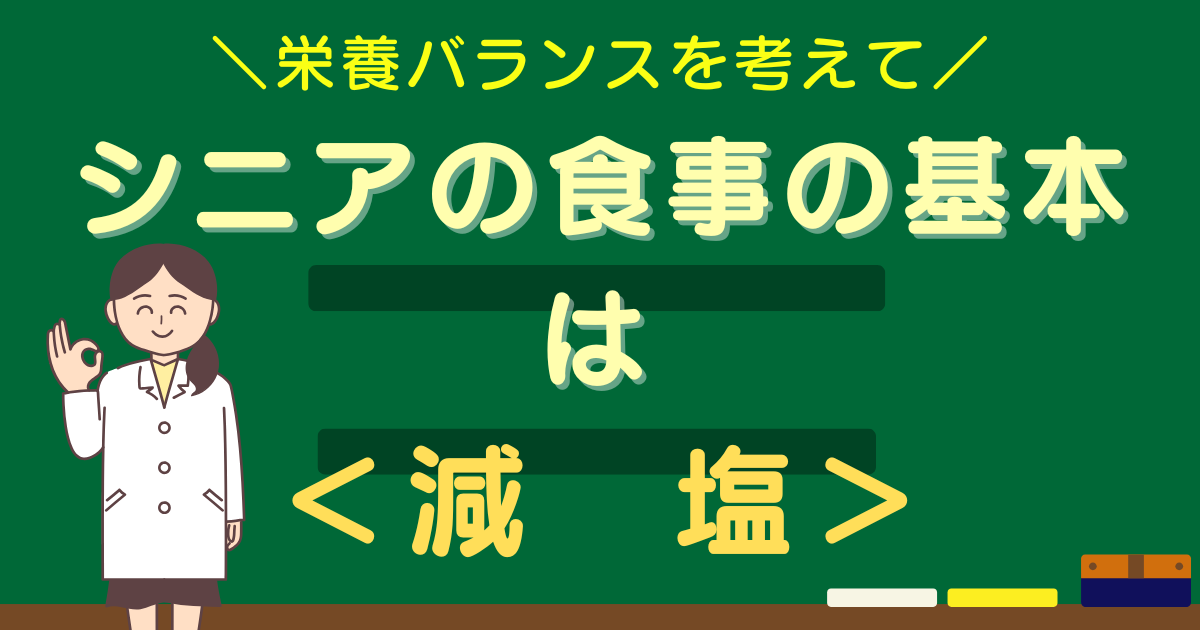
シニアのための減塩レシピ

少食でも栄養バランスを整えるコツ